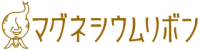水曜日にウイスキーに漬けたレーズンが、まあまあ漬かってきていたので、昼、フルーツバウンドケーキを作った。
パウンドケーキを作るのはかなり久しぶりである。2000年代末から2010年代頭にかけては、しょっちゅう作っていたが、今の部屋に引っ越してきてからは一度も作っていない。
よく作っていた頃は、小麦粉、バター、卵、砂糖の割合を、好みの割合にしていたと思うが、そんなものとっくに忘れてしまったので、卵3個の重さを量り、ほかの材料も同じ重さにした。150グラムだった。
バターに砂糖半分を少しずつ加えながらハンドミキサーで混ぜ、次に卵黄を少しずつ加える。卵白に残りの砂糖半分を少しずつ加えながらハンドミキサーで混ぜ、メレンゲ状にする。




ここで失敗。卵が古かったためか、メレンゲがうまく出来なかった。
しかし、ともあれ、バターと砂糖と卵黄のボウルに、メレンゲを3回くらいに分けて加えて、へらで混ぜる。メレンゲが残らない状態に混ぜたら、洋酒に漬けたレーズンに小麦粉をまぶし、ボウルに足して混ぜ、ミックスナッツを包丁で半分に刻んで、それも混ぜる。

生地を型に入れ、170度に熱したオーブンに入れ、50分焼く。40分くらい経った時に外から除くと、ちゃんと膨れていたのでホッとした。型は先週100円ショップで買ったやつで、長さが24センチくらいあり、150グラム材料でちょうどいいくらいだった。


思い出した。以前は短い型二つに分けて作っていたものだった。
50分が経過してから、すぐに型を外に出す。型にバターなどは塗っていないが。冷えるとケーキが少し縮むので、型とケーキの間に隙間が出来る。その性質を利用して出しやすくするため、型を逆さまにし、膨らんでいる部分が浮くように両端の角を台に乗せた。
小一時間ほどしてから、ラップを敷き、逆さまにした型をゆすると、ケーキが下向きにとれた。そのままケーキ全体をラップにくるんで冷蔵庫に入れた。

自分の作り方は、卵を卵黄と卵白に分け、卵黄は先に混ぜておいたバターと砂糖に加え、そこに小麦粉を加え、卵白をメレンゲにして最後に加えるというもの。これは、シュガーバッター別立て法というらしい。
メレンゲを作らず、バターと砂糖を攪拌したら、全卵を足し、最後に小麦粉を加えるやり方がある。これは共立て法。
あと、先に全卵と砂糖を混ぜ、小麦粉を加えたあと、最後に溶かしバターを加えるやり方が、ジェノワーズ法。スポンジケーキを作るやり方らしい。そういえば、大昔に妹と母がホールケーキを時々作っていたが、あれはこのやり方だったのかもしれない。ただ、妹と母のレシピは明らかにバターが多過ぎで、4分の1かけ食べると1キロ太った。
別立て法で作るようになったのは、パウンドケーキを作り始めるより前に、カステラ作りを試していたためだろう。カステラはバターを使わないため、膨らませるためにはメレンゲが絶対に必要だった。で、自分の中にメレンゲ信仰みたいなものが生まれ、そのあとにパウンドケーキを作り始めた時も、メレンゲを最後に投入するやり方を自然に導入していたのだ。
しかし、メレンゲ頼りにする分、バターに空気を含ませるプロセスは、それほど重要視していなかったきらいがある。実はそちらの方が重要なのだということを、なんとか法かんとか法が書かれているパウンドケーキレシピのサイトで知った。
夜、編み作業をする。とりあえずゴム編み部分を進め、絵柄手前の段で終わった。絵柄段は、一段につき色数が5色以上あり、しかもすべてグレー系なので、どの糸を編んでいるのかわからなくなることは必至だ。どうやって区別をつければ良いのか、うまい方法が見つかっていない。
冷やしておいたフルーツパウンドケーキを試食してみた。二日くらい寝かせた方が美味しいはずなので、冷えたとはいえ試食だ。

レーズンは沈殿防止のため小麦粉をまぶして混ぜ込んだのだが、すこし沈んでしまった。材料費をすべて1:1にしたため、こってりするかと思ったが、案外普通だった。卵感がやや強かった。
次に作る時は、レモン果汁を足した方が良いだろう。その方が、味がくっきりするはずだ。
夕食におでんを作って食べた。
無駄に起き、3時近くに就寝。