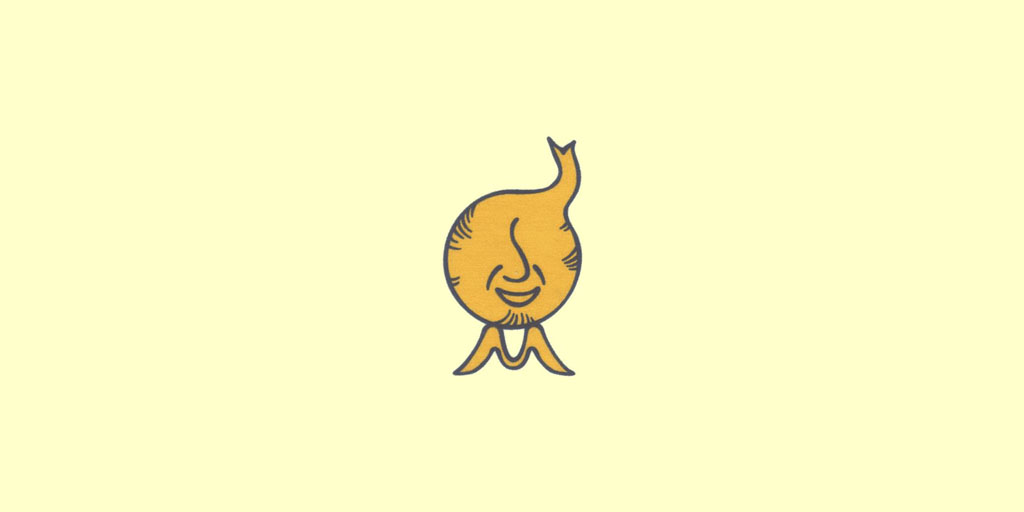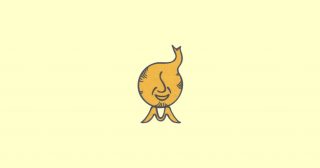朝、ジョギング。
青梅街道を、ラーメン二郎荻窪店まで走った。
長谷川康夫『つかこうへい正伝』読む。
青梅街道の「甲斐」で、昼飯につけ麺を食べる時に持っていったのだが、読み始めたら止まらなくなり、結局丸一日かけて500ページを一気に読了してしまった。
タイトルにある通り、つかこうへいの伝記だ。
1982年のつかこうへい事務所解散までのことが綴られている。
時代区分は大きく二つに分かれている。
- 慶応時代に詩の同人誌「三田詩人」に加入してから、早稲田の劇団暫で活動するまで
- VAN99ホールから、西武劇場、紀伊國屋ホールまでの、つかこうへい事務所時代
1は、有名になる前のつかこうへいについて書かれた文章で、関係者への取材や資料が元になっている。
2は、つかこうへいのそばで芝居作りや原稿書きをした内部の人間としての述懐だ。
1で面白かったのは「三田詩人」で同人だった堀田百合子の証言だ。
演劇を始める前のつかこうへいについて語れる唯一の人らしい。
「郵便屋さんちょっと」に出てくる《ゆりの看護婦さん》のモデルは彼女のようだ。
つかこうへいが恋愛感情を抱いていたのは間違いない。
若き《金原くん》を評した彼女の言葉が「彼って利にさといでしょう」というところに、品の良さを感じる。
つかこうへいが撮った彼女のポートレイトは、それを十分に感じさせるものだった。
「三田詩人」を辞め、演劇を始め、はったりと強烈な上昇志向で、若き日のつかこうへいは周囲を自分のペースに巻き込んでいく。
大学を中退し、鈴木忠志の知遇を得、早稲田小劇場の稽古場に通いながら演出を学び、やがて自らも早稲田の学生劇団である「暫」に乗り込み、自作の戯曲を演出するようになる。
その時に学生として参加したのが、平田満、三浦洋一、井上加奈子だ。
暫で活動中に岸田戯曲賞を受賞し、VAN99ホールに進出してからが、2の時期になる。
1974年から1982年までがこれにあたり、つかこうへいブームと呼ばれるのもこの8年間をさす。
たった8年の間に、多くの作品を上演している。
特に、1980年からの2年間はすさまじい。
「蒲田行進曲」の上演と、直木賞受賞、映画「蒲田行進曲」もこの時期に含まれる。
文字通り、人気がピークにさしかかった時に、演劇活動を休止したのだ。
長谷川康夫はつかこうへいが早稲田で活動していた頃から、裏方として様々な手伝いをしてきた。
後に役者としても活動するようになるが、メインの役どころというより、執筆の手伝いや、代役で口立ての台本作りを助けるなど、側近としての働きの方が大きい。
白水社の『つかこうへいによるつかこうへいの世界』には、「蒲田行進曲」の稽古場日記が収録されている。
長谷川は、つかに罵倒され続け、ついには主役の《ヤス》の座を柄本明に奪われてしまう。
この日記を構成したのは、長谷川本人らしい。
自分のことゆえに、自虐的に書けたらしいのだ。
つかこうへいは、芝居だけでなく、小説やエッセイの執筆も、口立ての手法を用いていたという。
平田満や長谷川をマンションに呼びつけ、設定を指示し、二人が書いたものに赤で書き加えて仕上げる。
口述筆記とは違い、これは書く人間のセンスも必要となる。
つかが書けなかったというわけではなく、他者の肉体を介した口立てという方法論が、その頃には染みついていたということかもしれない。
岸田戯曲賞を取る前に「新劇」に掲載された鈴木忠志や別役実論は、大変緻密な論理構成で、面白い読み物だったらしく、なぜそういうスタイルの文章をその後書かなくなったのかを、長谷川は本書で疑問視していた。
そういえば1992年だったか、岸田戯曲賞の選考委員として、つかが選評を書いたことがあった。
連載エッセイとワケが違うから、その文章にはいつものサービス精神はなく、その作品の受賞を自分が肯定するに至った理由を、論理的に書いていた。
たぶん、そういうスタイルの文章を書いた、例外的ケースだったのだろう。
1982年の活動休止後、7年のブランクを経て、つかこうへいは演劇界に復帰する。
オレが直に知っている《つか芝居》はこの時期からのものだ。
そして本書では一切触れられていない。
70年代のつかこうへいは、理不尽きわまりない魔王のようだった。
役者を育てようとする気持ちは、のちの北区つかこうへい劇団時代とは違っていたかも知れない。
「まして早稲田である。犬猫同然に扱ってやった」
という文が、『つかこうへいによるつかこうへいの世界』の、自作年譜にある。
この差別意識でもって、常識では考えられないほど役者を追い込んだことが、70年代つか事務所の俳優たちを生んだのではないか。
復帰後のつかこうへいからは、役者をちゃんと育てようとする、親心に似たものを感じる。
厳しさの根っこにあるものがどこか違う。
たぶん、70年代のつかこうへいと、90年代以降のつかこうへいは、別の人間なのだと思う。
本名・金原峰雄本人だけでなく、平田満、風間杜夫、長谷川康夫もまた、《つかこうへい》の一部だったのだ。
売れる前はみんなに飲み代を払わせ、売れてからはみんなに払わせたことがないというエピソードは、そのことを示していると思う。
大変面白い本だった。
つかさんは、人々を巻き込み、自分の中に憑依させ、自身をメディアのようなものにした演劇人だったのだという認識が、自分の中にできた。