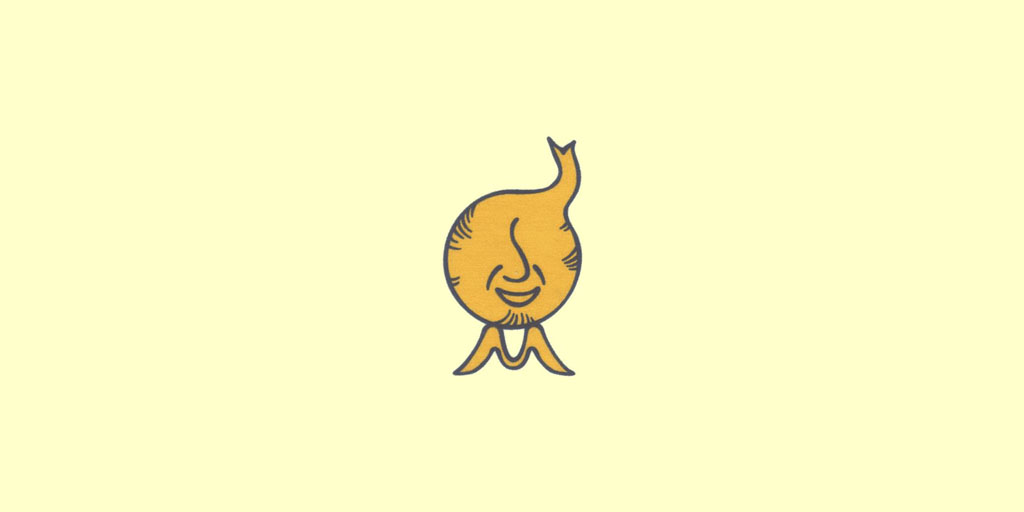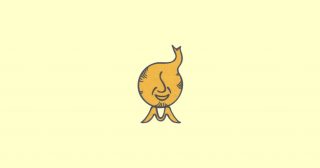花粉の季節は峠を越えたか?
個人的にそう思う。
というより、今年は飛散量の割に、ほとんど花粉に苦しむことはなかった。
たまに目がかゆかったり、くしゃみが出たりしたが、風邪をひいた時に比べたら全然大したことはなかった。
マスクもしなかった。
いい傾向だ。
斉藤孝『質問力』読了。
うまい質問はコミュニケーションを円滑にし、相手との相互理解を深めるという内容。
具体例から帰納して、いい質問の法則が導き出されている。
だが、その法則からいい質問が作れるかといえば、これは疑問だ。
頭ではわかっていても、実際にやるとどうもうまくいかないということになりそうだ。
つまりこの本の意義は、会話の折に何気なく発するに、注意を向けさせることにある。
いわば地ならしだ。
コミュニケーション技術における、啓蒙的パンフレットだといえる。
『黒部の太陽 ミフネと裕次郎』読了。
撮影にまつわるドキュメンタリーも面白かったが、完全収録されたシナリオに読み応えがあった。
『黒部の太陽』に関しては、石原慎太郎の『弟』にも記述がある。
五社協定の圧力に三船敏郎が及び腰になり、製作から降りそうになってしまい、裕次郎は兄に(生まれて初めて)弱音を吐いた。
慎太郎は五社の人間に会い、映画に協力している関西電力が100万枚のチケットを買い取ることなどを話し、はったりをかました。
の三船敏郎が安心できるように根回しをしたというニュアンスがあり、身内びいきの意図が感じられる。
五社協定とこじれる最大の要因となったのはだった。
日活に断りなくと記者会見で発表したことが、日活の態度を硬化させた。
裕次郎側のマネージャー、中井氏の作戦だった。
あくまでもフェアに解決した上で製作をしたかったらしい三船にとっては、こうした抜き打ち作戦は意に添うものではなかったらしい。
三船プロの社員を養うため、五社の仕事を蹴るわけにはいかないという事情もあった。
『ミフネと裕次郎』を読み、そのあたりの葛藤がわかった。
『黒部の太陽』は記録的大ヒットとなったが、石原プロはヒット作を続けて製作することに失敗し、多額の負債を抱えて映画製作を断念する。
その後『太陽にほえろ』『大都会』『西部警察』などの刑事ドラマで大当たりし、経済的に大きく盛り返したが、裕次郎の存命中ついに映画製作を再開することはなかった。
『黒部の太陽』撮影時の三船敏郎は、40代の半ば。
おのれのためだけでなく、身内のことを考えたのは、性格もあるだろうが、年齢のこともあると思う。
石原裕次郎がその頃の三船敏郎と同じ年齢になったのは、1981年だ。
その年裕次郎は、胸部大動脈瘤の発作を起こし、大手術をしている。
裕次郎が死んだら石原プロはどうなるのだろうという危惧を皆が抱いたであろうことは想像に難くない。
それは退院後の裕次郎にとっても同じことだったろう。
もし『黒部の太陽』の頃、裕次郎が三船と同じく40代半ばだったら、計画は頓挫していたのではないか。
また、二人とも30代前半だったとしたら、五社と必要以上の軋轢を生んで、映画生命を絶たれていたかもしれない。
昭和30年代、深川に住んでいた親父は、日曜になると場末の映画館で映画ばかり見ていたそうだ。
「『黒部の太陽』は見た?」
「見てない。その頃はもう江戸川区に来てたから、映画見る金あったら、呑んでた」
「じゃあ映画見てたのはそれ以前か」
「豊洲に会社の独身寮があって、日曜で誰もいないと映画見るしかすることないから、一般封切り以下の安いとこで3本立てとか見てたなあ」
「どんなの?」
「時代劇は不思議と見なかった。日活だなやっぱり。入場料いくらだったかな…50円くらいで見れたと思うけど」
「場末だね」
「そう、場末。トイレなんか汚くて入りたくないようなとこでさ」
「見たのはやっぱり裕次郎?」
「いや、裕次郎はまだ田舎にいる高校生の時だな」
「じゃあ小林旭だ」
「そう、旭。裕次郎は見なかったな。飲み屋の女の子なんかが、裕次郎と旭のどっちがいいかなんていう話をよくしてた」
「どっちがいいって?」
「旭だな」