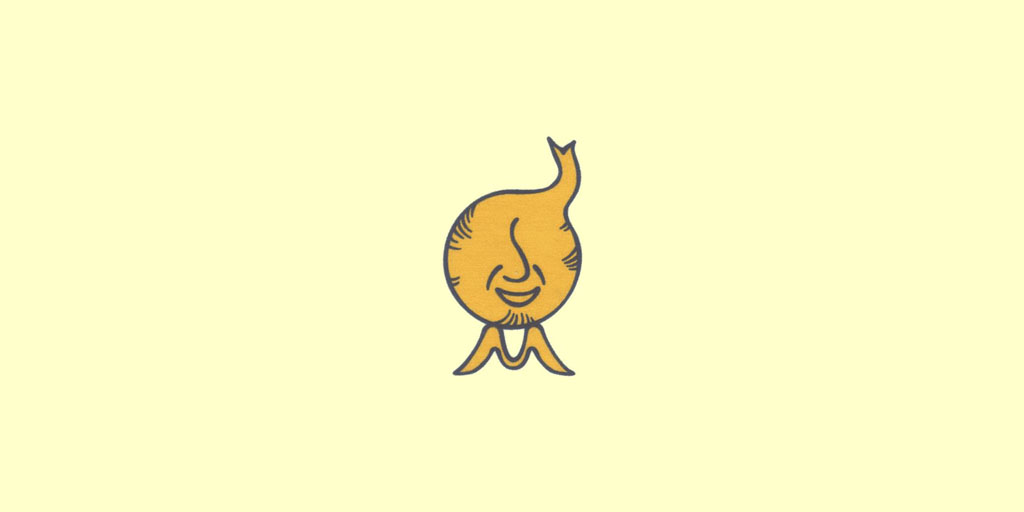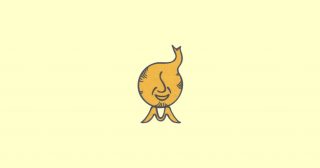天ぷらが食いたいとか言っておきながら、今日もインスタント食生活である。
朝っぱらからラーメンだった。
昼は弁当を作ることで、食生活がインスタント色に染まるのを防いだが、夜はまた韓国の辛ラーメンでインスタントに逆戻りだ。
インスタントラーメンを特に旨いと思ってるわけじゃないのだが、食いたいことは食いたい。
だから別に不満はなく、食い終わってから、
(いいのかなこれで)
と思っている。
?橋治「絢爛たる影絵 小津安二郎」読む。
監督会の席上で吉田喜重監督に詰め寄った事件については、かつて吉田喜重の「小津安二郎の反映画」で読み、知っていた。
他の小津本でもその事件に関しての記述があり、それらからイメージしていたのは、何時間も酒を飲みながらひたすら黙って対峙している小津安二郎と吉田喜重の絵だった。
ところが、そんなに穏やかな状況ではなかったと、本書は述べている。
小津監督が言ったとされる言葉をそのまま引用してみる。
「俺は木下や小林は好きだが、吉田君、君は気に入らんね。君に俺のことがわかってたまるか!俺はな、橋の下で菰をかぶって春をひさぐ夜鷹なのさ。吉田君、君は橋の上にいるのだろう?橋の上に立っている人間なんだろう。橋の上に立って、橋の下の世界を見下しているんだろう。俺は確かに夜鷹だよ。でも、それで良いと思ってる。いや、映画作家なんてものは、所詮そんなもんだ。橋の下で客の袖を引くのさ。橋の上になんて、とっても畏れ多くて立てないね」
これらの言葉をひと息にまくし立てたわけじゃないが、一つにつなげて長台詞にした方が、言わんとしていることがわかりやすいような気がする。
小津監督を諫めたのは木下恵介監督だという。
その諫め方も面白い。
「小津さん、あなたも若い頃は吉田君みたいな映画を撮っていたじゃありませんか」
木下恵介の諫言を小津安二郎は笑って受け入れたため、場は和んだというが、監督会の末席に連ねる吉田喜重のいたたまれなさは最後まで解消されなかったという。そりゃそうだ。
小津安二郎がなぜこの時に限って絡んだかについては、関係者の解釈がまちまちだ。
少なくとも式の発憤とは違うようだ。
の喩えで、映画作家は所詮賤業だということを伝えたかったのか?
わからない。
いずれにしても、小津安二郎は決して撮りたいものだけを好きなように撮っていたわけではなく、松竹のトップというおのれの立場と、作品の興行価値という二つの要素に対して、絶妙の距離感で作品を作り出してきたということはあるようだ。
状況に反発するでもなく、かといって流されるでもなく、それを最大限に利用し、なおかつ自分のやりたいことを盛り込めるだけ盛り込む。
こうした映画作りは、現実適応能力の高さに裏打ちされていたんじゃないかと思う。
とは、その適応能力をさしてはいないだろうか。
映画作家としての矜持を保ち続けるために橋の上に居続けることは、傍目にも格好良い。
だけど、それで銭が稼げるわけじゃない。
銭を稼ぐためには橋の下で客を引かなくてはならない。
そして橋の下にいる人間のことなんて、橋を通る人々にはわからない。
しかし、映画監督がすべて橋の下の夜鷹になれるとは思わない。
欄干から糸を垂れ釣りをする人もいるだろうし、ござを敷いて道行く人に施しを受ける人もいるだろう。
溝口健二監督はさしずめ、橋のたもとで息を潜める辻斬りだろうか。
夜鷹は客が自分の意志でやってくるのだから、そんなに悪いもんじゃないと思う。
土左衛門になってしまう監督だっているのだし。