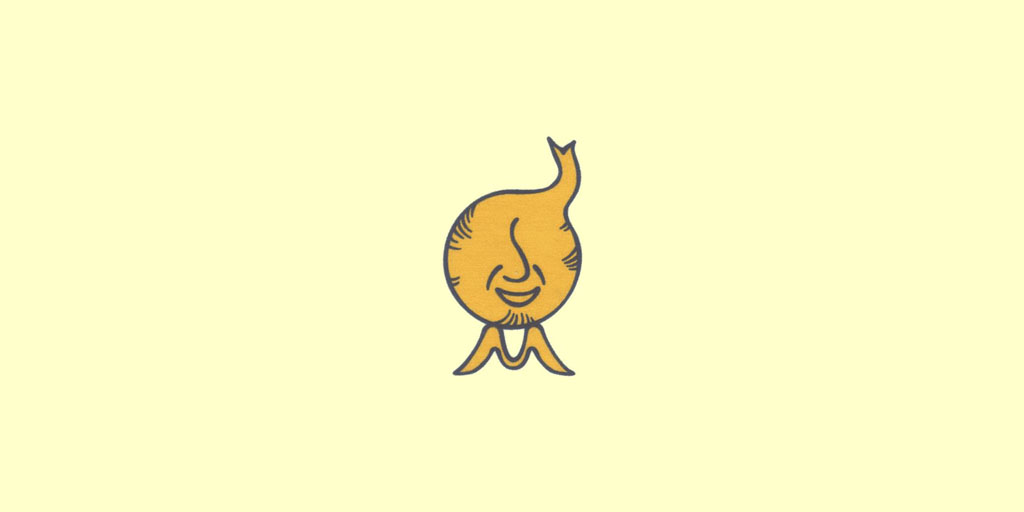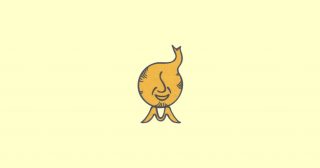山かけご飯、塩鮭、小松菜の味噌汁、レトルトのハンバーグ、目玉焼き。
妙にたくさんのおかずで朝飯を食った。
そのせいか、夕方4時過ぎになるまで腹は空かなかった。
椎名誠『海ちゃん、おはよう』読了。
長男の岳くんは『岳物語』『続岳物語』という作品で語られている。
思春期になって初めて作品を読んだ彼は、父親に対して怒りを覚えたそうだ。
そのため父子関係は一時期微妙だったらしいが、思春期とはそういうものだ。
長女の葉さんのことはこれまでほとんど書かれたことがなかった。
今回の作品では、椎名誠の新婚時代と長女誕生後の話が中心になっている。
一応小説の体裁だから、奥さんの<いちえさん>は<なみえさん>というふうに、名前が若干変えられている。
しかし、これまで謎のヴェールに包まれていた新婚生活がついに明かされることに感慨を覚えた。
『哀愁の街に霧が降るのだ』では、羽生恵里子という謎の美人が登場するが、彼女がいちえさんをモデルにしているのかはわからない。
その本を書いていた1981年頃は、夫婦仲がぎくしゃくしていたらしいし、いちえさんがノイローゼ状態になるのはそれから間もなくのことだ。
『かえっていく場所』では『彼女の感情が壊れた』と表現をしていた。
『海ちゃん、おはよう』では、そんないちえさんとの新婚生活が綴られている。
(椎名さんも奥さんのことをこうして書ける年齢になったのだなあ)
と思った。
『哀愁の街?』の頃は、奥さんとの出会いを書くなんて、恥ずかしくてとてもできなかったろう。
いちえさんは木村晋介と同じ高校だった。
『哀愁の街?』で書かれた克美荘集団生活時代、木村さんがいちえさんを部屋に連れてきたらしい。
椎名さんが彼女とつき合うまでの課程は、普通にさわやかなラブストーリーだった。
お互い将来の夢を語り合い、
「外国でどーんとなにかやりたい」
と言う椎名誠に対し、
「早く白髪になって、小袖の着物を着て銀座を歩きたい」
と言ういちえさんとの対比がとても素敵だ。
夫婦げんかの話もおもしろかった。
子供ができる前、逆上して原っぱでいちえさんを一本背負いして以来、しばらく許してもらえなかったとあるが、これは当たり前だろう。
以来、けんかはもっぱら口げんかとなる。
娘が熱を出した時の口論など、生々しいほどリアルに書かれていた。
真摯で聡明なイメージのあるいちえさんが、怒って挑戦的な口調で夫を難詰するシーンには、彼女もそういう時代があったのだと妙に安心させられた。
夕方、池袋で鶴マミと待ち合わせ。
仕事帰りの彼女から、稽古場の登録証を受け取った。
そのまま実家へ。
夜、台本書きをしようと思っていたが、テレビで『もののけ姫』をやっていたので、久しぶりに全部見る。
息もつかさず集中して見た。
この作品は、DVDで繰り返して見た方が楽しめる。
生と死、村人と野武士、森と人間の相克といったテーマは、一度見ただけではわからない。
見れば見るほど、結局明示されなかった答えへの希求が、自分の中に芽生えてくるのがわかるのだ。
そして希求させる力は、批判者によって<説教くさい>と言い換えられていた。
しかし、作品を見直してわかるのは、説教的なシーンはむしろ少ない。
アシタカは、
「双方が生き延びる道はないのか」
と言っているが、答えの出ない問題に対する絶望が浮き彫りになるだけで、説教になってはいない。
初見の観客が感じたもどかしさは、アシタカのもどかしさと類似している。
(どうにかしたい、でも、どうすればいいのだ?)
対立は、エボシがシシ神を殺した時点でピークに達する。
決して引けない者同士の対立がドラマになれば、あとは死屍累々というのが一つの定番的解決だ。
たとえば黒澤明が『乱』のシナリオ最後に書いた、
『惨!』
のひとことのように。
『もののけ姫』ではそうならず、アシタカがシシ神の首を返すスペクタクルシーンで、ラストにかけて強引にカタルシスが表現されていた。
しかし、答えの出ない問題に翻弄されてきたアシタカの物語と、首を返して呪いも解けるアシタカの物語は、まったく別次元のものだ。
キーやテンポの違う曲を強引につなげたように、スペクタクルシーン以降で我々はやや面食らうことになる。
この作品を見る時は、
<問い> 冒頭シーンからエボシがシシ神を殺すまで
<答え> でいだらぼっちの巨大化からラストまで
という構成を意識すると、大変面白く見ることができるのだ。
他の作家なら<答え>部分をどう処理したかを考えながら見ると、なおさら面白い。
ふと、手塚治虫『アドルフに告ぐ』を思い出した。
あの作品も、お互い引けない者同士の対立を描いており、幼なじみだった二人のアドルフは最後に殺し合いをする。
ただ、対立が極限にさしかかる時に、歴史的事件という恩恵を受けている。
(どうにかしたい、でも、どうすればいいのだ?)
葛藤が限界に達した時にいつも、ドイツの降伏などといった大事件が起こり、登場人物は歴史の本流に巻き込まれていく。
殺し合いをする頃、事態は手遅れになっているのだ。
意地悪な言い方をすれば、答えの出ない問題に読者の目を向けさせ、いよいよ答えを出さないといけなくなったら、歴史を利用して問題をうやむやにしている。
(ああ、やっぱり戦争はいけないよねえ)
(どうしてみんな仲良くできないんだろう)
読者の感動の裏には白痴化した感想がある。
が、その能力は、物語を作る者にとって決して罪ではない。
むしろその能力をさして人は<才能>と呼ぶ。
我々は涎を垂れ流し、惚けた表情で「もっともっとー」と次の作品をせがむ。
手塚治虫は天才だ。
宮崎監督は生来の生真面目さからか、問題の本質をそうやってうやむやにすることに嫌悪感を覚えるたちなのかもしれない。
だからといって『もののけ姫』にある多くの対立構造を解決するうまい手段を見つけられるわけでもない。
そこで、どうせ解決できぬならと、自分の<夢>を盛り込んだのではないだろうか。
この場合、夢は実現不可能であるはずだ。
実現可能なら、そのプロセスをはじめから映画にすればいいのだから。
実現不可能な夢は、人によっては<世迷い言>と映る。
『もののけ姫』が嫌いな人は、この<世迷い言>に反応しているのだと思う。
夜1時から台本書き。
やはり、深夜の方が筆が進む。