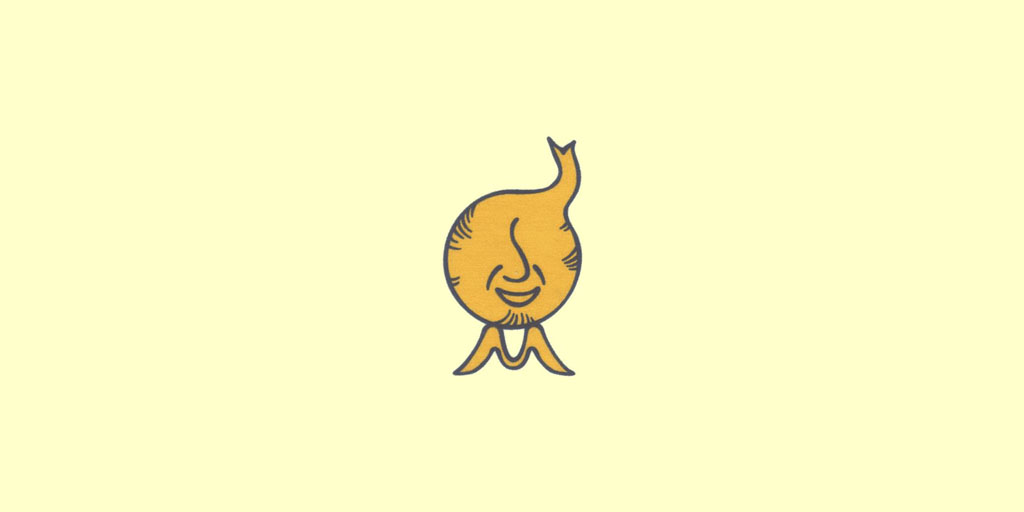筒井康隆『夢の木坂分岐点』を久しぶりに読む。
本を積極的に読むようになったのは17歳の夏休みからだった。
退屈な夏を過ごしていて、このまま人生が終わってしまいそうに感じ、せめて本でも読もうというのが動機だった。
どんな本でも手当たり次第というわけではなく、どうせなら現代文の成績向上につながるものを読もうと思った。
夏目漱石の『こころ』や『それから』、ヘルマン・ヘッセの『車輪の下』など、新潮文庫の100冊にエントリーするようなものばかりだった。
読書経験の乏しい17歳の小僧が、名作ばかり義務的に読んでも、面白いと思えるはずはない。
その頃に読んだ本で、今でも記憶に残っているものはほとんどない。
あるとすれば、のちに読み直したものだ。
『夢の木坂分岐点』を読んだのは20歳の時だった。
バイトに行く途中、電車の中で読む本を買うため本屋に寄り、手にしたのがこの本だった。
数ページ読んで、普通の本ではないと感じた。
買ったその日に読了し、人生を左右する一冊にやっと出会えたと思った。
17歳の夏休みから、3年と半年が経っていた。
主人公は、夢と現実を等価と見なし、どちらも同じように一生懸命生きようとしている。
夢の中の自分は、サラリーマンであったり、兼業作家であり、専業作家であったり、作家になりきれないサラリーマンであったり、サラリーマンをやめた作家のなりそこないであったりする。
それぞれの関係性を線で結ぶと、サラリーマン兼業作家の自分が思い描く専業作家の自分が書いた作品の主人公が作家になりきれないサラリーマンの自分でその自分が原稿用紙に向かって書いている小説の主人公がサラリーマンをやめた作家のなりそこないという案配になる。
こう書くと非常に複雑に思えるが、それぞれの自分が並列に描かれているため、異なる次元に存在する別々の人生を眺める趣があり、読みづらさは感じない。
初めて読んだときは、多元宇宙SFのような面白さと、サイコドラマの演劇的な側面に惹かれた。
二十代後半から三十代にかけて読み返したときは、夢を分析し己を知るに至るユング心理学的な部分に惹かれた。
今回はどんな発見があり、どんな部分に惹かれるだろう。
これから読むのだ。
ウイスキーをちびちび飲みながら読むのだ。
すでに喉が猫のようにゴロゴロ鳴っている。
この愉悦、この快楽。