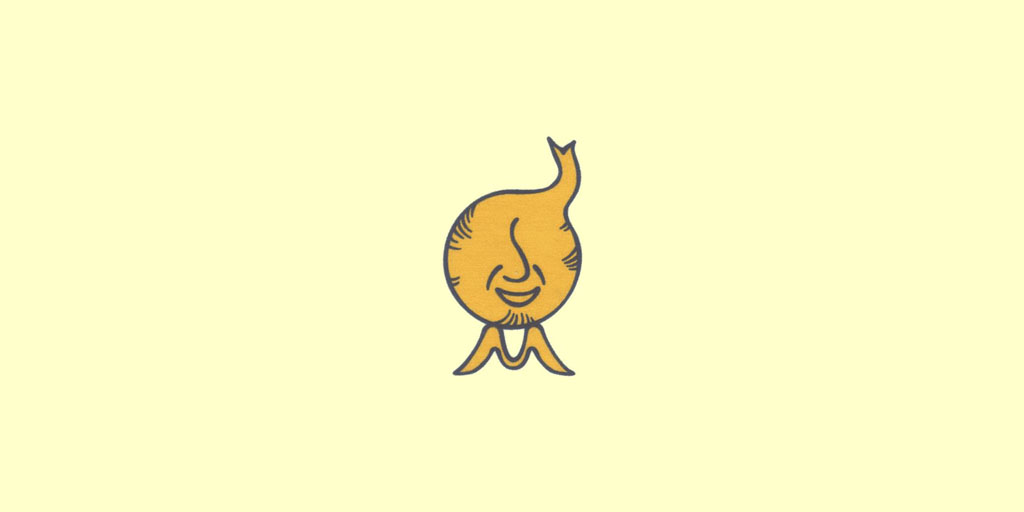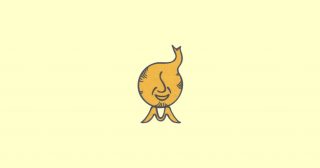『カラマーゾフの兄弟』3巻読了。
1巻と2巻で引き絞ってきた弓矢が一気に放たれるかのように、物語は怒濤の迫力で展開する。
長男ドミトーリィの話が中心。
1巻や2巻を読むだけでは、女好きでだらしなく、暴力的で破滅的なこの男を好きになれなかった。
だが、3巻を読み進み、グルーシェニカの古い恋人の化けの皮をはがすあたりから、心打たれるようになった。
彼にではない。
限りない高潔さと、限りない下劣さが、一人の人間に同居していることにだ。
ドミトーリィの饒舌には、人間の罪深さや慈悲深さのすべてが詰まっているようで、ただひたすら圧倒される。
もはや、好きとか嫌いとかいうレベルではない。
新潮文庫版よりも、饒舌の迫力が伝わりやすくなっている。
巻末の読書ガイドも、人によっては「うざったい」かもしれないが、深読みするにはとても助けになる。
光文社古典新訳文庫。
このシリーズは良いなあ。
バルザックとかやってくれねえかなあ。
『谷間の百合』新潮文庫版が、全然わかんなかったのだ。
夕方、中目黒のウッディシアターへ。
イルカ団公演『デザート』見る。
イルカ団の芝居を見るのは5年ぶりだ。
そしてこの作品は再演だ。
タイトルに見覚えがある。
今回は、旧知の権田成美さんのチケットで見ることにした。
受付にて、杉ちゃんと会う。
権田さんも杉ちゃんも、かつてイルカ団で共演したことがある。
オレが出たのは今から10年前。
マグネシウムリボン旗揚げ直前の7月だった。
その頃のイルカ団は<淡々>と<まったり>の合間を漂う会話を特徴とする芝居をしていた。
今回の『デザート』は、そんな<初期イルカ団>の味わいを残しつつ、ミステリー色の強いストーリーとなっている。
喫茶店の客が、爆弾魔の仕掛けた爆弾もろとも、店に閉じこめられる話だ。
序盤は人物紹介シーンが続き、そこは昔のイルカ団と変わらない。
爆弾が見つかってからの展開は、違う作家の芝居を見るようだ。
誰が犯人なのかわからず、パニックがあおられる展開は、まことに上手い。
高橋いさをの『ボクサア』を思わせる。
イルカ団らしいなあと思ったのは、ラストの突き放し方だ。
真犯人が名乗り出て、どんでん返しを見せると、速やかに爆弾を爆発させ、あっという間にカーテンコールへ。
序盤を切りつめ、ラストをもう少し引っ張る作りをすれば、非常に質の高いミステリー劇になるのだけど、その完成予想図のウェルメイドっぽさは、ベタと言えばベタだ。
主宰で作・演出の小林英武君は、かつてカーテンコールすらやらないこともあった。
そのあたりの、
(わあ、えんげき)
みたいな感覚に対し、独特の距離をとっていたように思う。
それが嫌悪からくるのか羞恥からくるのかはわからない。
ただ、さすがに今ではカーテンコールはする。
終演後、英武君と挨拶。
「これから飲み、どうです?」
と誘われる。
「でも、知らない人ばかりだし」
「オレと権ちゃんがいるじゃないですか」
「そうだね」
久しぶりだし、行ってみようという気になる。
劇場外で、賢さんと会う。
5月の「アブソリュート・ゼロ」で権ちゃんと共演したため、今回見に来たのだろう。
「塚本さん、出たことあるんでしたっけ?」
「ボク、過去2回出てますよ」
と会話する。
中目黒といえばおなじみの『大樽』で飲み。
今回の出演者はほとんどが20代前半から中盤の若者で、オーディションで集めたと英武君から聞く。
英武君とは12年前に出合った時から、正式に名前で呼んだことがない。
彼のあだ名は「ヒロ」なのだが、その名でさえ呼んだことがない。
呼ぶタイミングを逸してしまうと、取り返しがつかなくなるものだ。
飲みながら話していると、お互い大人になったなあとしみじみ思った。
英武君には、昔とは違う落ち着きが備わっていた。
身も心もバラバラになるほどの嵐を経験し、それでも板きれを集めて筏を造り、懲りずに同じ目的地を目指すような愚直さが、好ましく映った。
遅れて権ちゃん来る。
10歳も年下の共演者から、
「ゴンちゃん」
呼ばわりされている。
そのことに違和感は感じられないが、それでも10年分お姉さんになり、声には艶が増した。
飲みながら、芝居を続けるということについて、思いがけず深い話をする。
10年前に共演した役者が、10年後の今、同じ劇団の芝居に出ている。
生き延びた戦友と再会したような気持ちだ。
言葉はセンチメンタルになっていく。
そのまましゃべり続けると、鼻持ちならなくなりそうだったので、一足先に帰ることにした。
英武君より名刺をもらう。
「今度芝居やる時は教えてください。観に行きますから」
と言われる。
「ありがとう」
と答える。