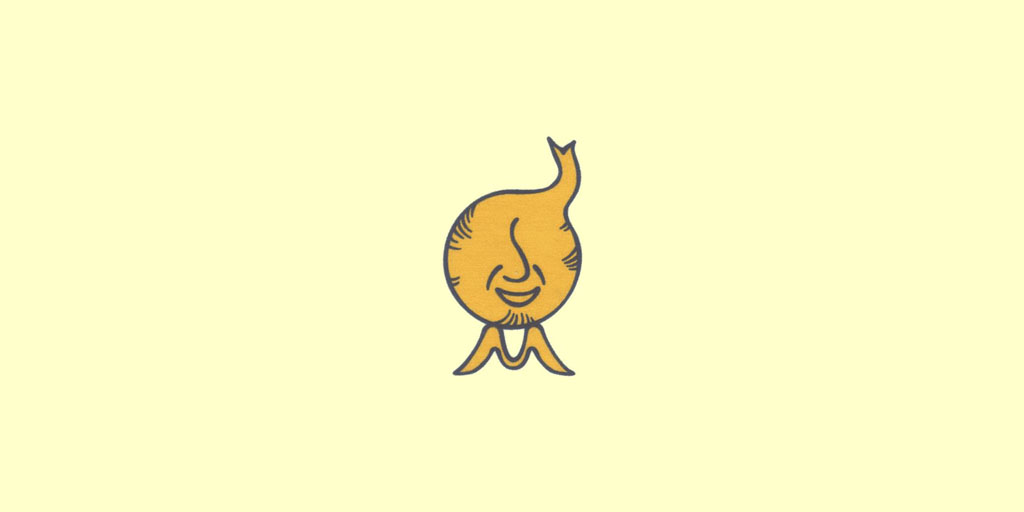真夜中2時半に目が覚めた。
寝ぼけてではなく、冷たくて甘いのが食べたいなあと思いながらコンビニへ。
白くまを買って食べる。
そのまま4時半まで起きて『フロスト始末』下巻を読む。
8時半にドアフォンの音で目が覚めた。
玄関のカメラを見ると、男が立っていた。
配達ではなさそうだったので、無視することにした。
出ると大抵ろくなことがない。
昨日買ったエアーストーンを水耕栽培のエアーポンプに取り付け、トマトの誘引をしていたら、さっきの男が庭の方にやって来た。
「来月、外装工事をしますので、ヨロシクお願いします」
屋上や階段の防水など、ひと月くらいやるらしい。
「で、そちらどうします?」
男は、庭に植えていたトマトの蔓を指して言った。
脇芽を植えたもので、蔓を誘引することなくほったらかしたので、地べたを這うように育っている。
「工事までに抜いておきますよ。いつからですか?」
「8月17日からです」
「いつまで?」
「9月末です」
「長いですね」
「ええ、砂利敷きにしますんで」
なんと。今まで土だったスペースが、なくなってしまうらしい。
男が去ってから、ポストに入っていたチラシを読んだ。
言われたことと大差ない内容だった。
砂利敷きになるということは、隣室やその向こうのスペースに植わった木々も伐採されてしまうのだろうか。
気分が落ち込んだ。ついこの前、ジャガイモ栽培に成功したばかりなのに。
しかし、水耕栽培という手がまだ残っている。
エアーポンプつきの植木鉢みたいなものだから、土がなくなっても野菜は作れる。
部屋の契約更新が今月末までということを思い出し、書類を整理した。
昼に不動産屋に行き、その足で吉祥寺に行き、なべさんの芝居を見よう。
なんならその後いっぱい飲むか、でなければ東小金井まで足を伸ばして、「宝華」で油そばを食べるのもいい。
そう思いながら割り印を押した。
ふと気づいた。割り印を押す箇所が二つある。
一つは自分。もう一つは保証人のだった。
保証人のサインと印鑑はもらっていたのだが、割り印を忘れていた。
昼前、走りに行く。
善福寺川沿いを5.3キロ。
オオタカの鳴き声が聞こえた。
契約更新には古い契約書も必要だった。
しかし、書類整理用のラック、チェスト、引っ越しの時にしまった段ボール箱の中を探しても見つからなかった。
探していて気づいたが、昔に比べて、持っているものが少なくなった。
だから探す場所も限られており、そこになければ、捨てたかあるいはなくしたのだと判断できる。
それでも、段ボールをあけると、15年前に買った両面テープが沢山出てきた。
さすがに、もう使わないと思い、ゴミ袋に入れた。
段ボールには工具類も入っていた。
そんなところにしまっていたら、使いたい時に出せないではないか。
これも、必要最小限のものを残して、取り出しやすいところにしまって、残りは捨てよう。
夕方実家へ。
カレーライス食べる。
夏の夕食にカレーライスは嬉しいものである。
「スイカがあったら最高なんだけどな」
そう言うと母が、
「先に言ってくれたら買っといたのに」
と言った。
高倉健の映画「ごろつき」をTSUTAYAで借りた。
しかしプレーヤーに入れても再生されなかった。
ディスクが古くなっていたのかもしれない。
この映画には、ブレイク直前の菅原文太が健さんの弟役で出ており、二人で流しをやり、「網走番外地」を歌う場面がある。
それだけが見たくて借りたのだ。
『フロスト気質』上巻、読み始める。
明け方、白くまを食べた後に、最新作『フロスト始末』を読み終えた。
作者が亡くなっているため、最後のシリーズとなる。
フロストシリーズを初めて読んだのは19年前の春だった。
その頃一緒に暮らしていたパートナーが、日頃世話になっているお礼にと言って、図書券をくれた。
5000円分くらいあっただろうか。
当時、本を図書館で借りる習慣はまだ無かった。
読みたい本は古本屋をめぐって買っていた。
だから、好きな本を5000円分買える状態というのはありがたく、早速あぶく銭ならぬあぶく券をもって近所の本屋に向かった。
武蔵小金井南口商店街の外れに小さい本屋があった。
好みの本が揃っていたので、向かいの大きい本屋よりもよく利用した。
その本屋で物色していると、文庫本コーナーで分厚い本が平積みになっていた。
『クリスマスのフロスト』という本だった。
帯には、どこそこのランキングで1位、という惹句。
ミステリーを読んだことはほとんどなかったし、買うのはためらわれたが、なにしろ手にしているのはあぶく銭ならぬあぶく券だ。
こういう時には普段読まないジャンルの本を読んだ方がいいのではないかと思い、手にとってレジに向かった。
面白かった。
複数の事件が同時に進行し、ある事件が別の事件と意外なところでつながっていたりしていて、それらが最後になって一気に解決されていく展開には爽快感があった。
だが、一番の魅力は何といっても、主人公ジャック・フロストのキャラクターだった。
読み終わってすぐに、シリーズ第二弾『フロスト日和』を買った。
これも面白かった。
当時、その二作品しか翻訳されていなかったので、読み終わると渇望感に苛まれた。
もっともっと読みたい、というふうに。
で、次に読んだのが、ロバート・ゴダードの『千尋の闇』だった。
これも、帯になんとかランキング1位とか、惹句があった。
フロストとは全然タイプが違う作品だったが、すこぷる面白かった。
ゴダードの作品はフロストよりも多く出ていたので、その後しばらくはゴダード作品ばから追いかけるようになった。
フロストに始まり、ゴダードにはまることで、ミステリーの楽しみ方を学んでいったわけだ。
しかし、フロストシリーズはミステリーだろうか?
原文がどうなっているのかわからないが、訳者・芹沢恵によるフロストの台詞には、フロスト節とでもいうべき語り口がある。
だから、殺人事件の捜査をしながら下品なジョークを飛ばしても、読み手は「よっ!待ってました!」と合いの手を入れたくなる。
正直なところ、前作『冬のフロスト』は、ミステリ作品としてではなく、そうしたフロスト節を堪能するために読んでいた。
ひょっとすると、事件が解決されなくても、満足していたんじゃないかと思う。
作家と読者の関係としては不健康だが、フロスト節にはまった読者にはわかってもらえるんじゃないかと思う。
シリーズには毎回、フロスト警部と対立する人物が登場する。
今回は、デントン署に配属されていたスキナー主任警部がそうだった。
デブで権高で、フロストを追い出すためにやってきた設定なのだが、役不足だなあと感じた。
たとえば嫌われ役レギュラーのマレット署長の場合、憎たらしい存在なのだけど、未決書類をめぐるフロストとのやりとりや、署長室でタバコを吸うフロストに気づいて慌てて灰皿を出すが間に合わず灰が絨毯に落ちるなどのお約束場面があり、「芸」を感じさせる。
前作では愚鈍すぎてイヤな印象があったモーガン刑事が、今回はとても面白かった。
フロストは彼のことを「ウェールズの芋兄ちゃん」とか、さらに縮めて「お芋くん」と呼んでいる。
そのお芋くんがフロストのことを「親父さん(おやっさん)」と呼ぶのが可笑しい。
頼まれた仕事で必ずへまをするという設定もいい。
二人が会話をするたびに、絶妙な刑事コントが展開しているみたいで、ニヤニヤが止まらなかった。
内容としては、事件の解決が尻すぼみのように感じられた。
残酷さに対して、犯人の器が見合ってなかった。
スキナーも、結果的には尻すぼみになってしまったし。
その代わり、フロスト節はシリーズ中一番面白かった。
よくも続くよ下ネタが、という感じだった。
が、女性が読んでも安心して笑える他愛ない言動だ
このバランスゆえに、どのシリーズもなんとかどこそこランキングの連続1位を成し遂げてきたのだろう。
あとがきに、新しいシリーズが別の作家によって書かれたとあった。
遺族の許可を得てのことらしい。
まだ翻訳されていないが、もしそうなるなら訳者は芹沢恵さん以外考えられないだろう。
と、そんな感想を持ったついでに、過去作品を読み直そうと思った。
で、『フロスト気質』上巻を、読み始めたというわけ。
この夏中に全作読み返せるだろうか?