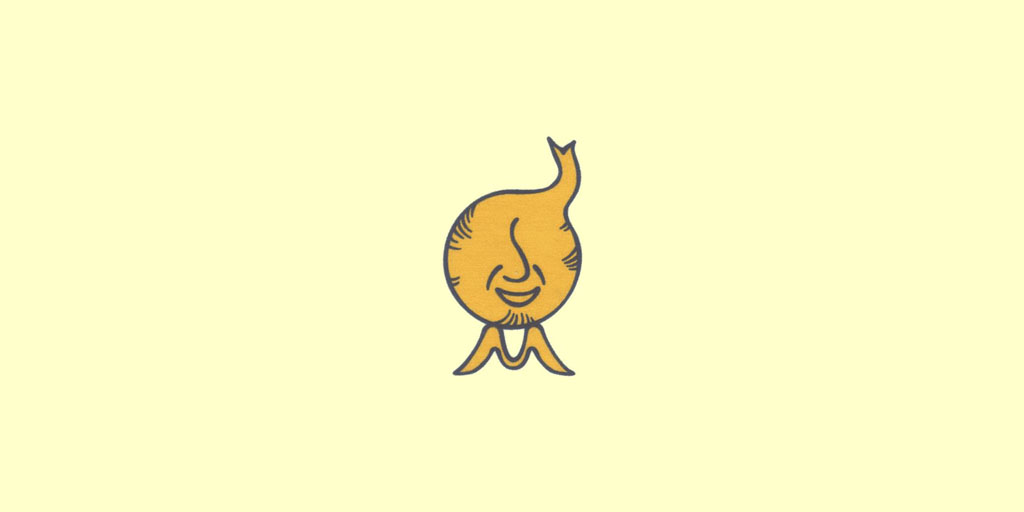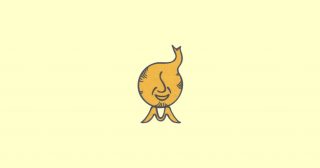昨日は最高気温18度と暑かったが、今日は冬の逆襲で10度前後だった。
『北風と太陽』はきっと今くらいの季節に書かれたのだと思う。
夕方実家へ。
牡蠣フライを食べる。
夜、親父から夢の話を聞く。
「最近、死んだ前の社長が夢に出てくるんだよ。夢ん中で俺は小学生なんだ。学校行くんだけど遅刻してるんだな。で、教室には社長がいるってことになってる。イヤだなあって思うんだけど、まあいいかって腹決めて教室に入ると、社長は休みだってことがわかってほっとするんだよ」
死んだ社長は両親の仲人だった。
「おっかしいんだよな。今の社長や、先々代の社長は一回も出てこねえんだ。前の社長の弟(親父の先輩)も出てこねえ」
先々代の社長が死んだ日のことは強烈に覚えている。
夜遅くにドアフォンが鳴った。
玄関に出たお袋は怪訝そうに戻ってきた。
「変ねえ、誰もいないわ」
悪戯にしては、遅すぎる時刻だった。
すると突然電話が鳴った。
お袋が出た。
「・・・えっ!」
それは先々代社長の死を知らせる電話だった。
直前に鳴ったドアフォンは誰が押したのか?
葬式が終わってから親父は言っていた。
「あれは、社長が俺に自分の死を知らせに来たんだな」
この時自分はまだ小さい子供だったが、不思議と怖さは感じなかった。
死とはそういうものなんだなあと思った。
1年以上の入院生活の末、母方の祖母が亡くなったのは、10歳の時だった。
学校から帰ると、友達の母親から電話があった。
昼間はうちに誰もいないため、もしも祖母の様態が急変した時にはその人に連絡がいくようになっていたのだ。
「健ちゃん、あのね、おばあ様が亡くなられたって・・・」
家族で一番初めにそのことを聞かされた。
パートから母が帰ってくるまで1時間くらいあった。
その間、子供ながら死について色々考えたと思う。
一番悩んだのは、どうやってその事実を母に告げればよいのかということだった。
祖母の死を告げると母は血相を変え、友達の母に電話をした。
どういう連絡があったのかを詳しく聞き、姉に電話をし、着替えてうちを出ていった。
母が出て行ってからしばらくして、妹が帰ってきた。
そして、同じく会社に連絡が行っていた親父も帰ってきた。
その夜、親父と妹と3人で叔父の家に行き、祖母の亡骸と対面した。
ものすごく緊張した。
それは生まれて初めて見る死だった。
葬式が終わるまでの数日、叔父の家に通い詰めた。
手伝わなければいけないことが沢山あったからだが、なにしろ10歳の子供だから、どこまで手伝えたかは怪しいものだ。
親戚一同が集まっている状況が妙に嬉しく、少しはしゃいでいた。
祖母は心臓が弱かった。
入院してしばらくは、かなり危ない状態が続いた。
かなり危ないらしいという時に、見舞いに行ったことがある。
祖母は鼻にチューブを差し込まれた状態で苦しそうにあえいでいた。
いとこの姉ちゃんが、
「おばあちゃん・・・」
とつぶやいて絶句した。
親父は、祖母の意識を保たせるため、
「ばあちゃん? 孫たち来たよ。わかる?」
と、声をかけていた。
苦しそうにあえいでいた祖母と目が合った。
祖母は、感に堪えないといった顔をして、両手を伸ばしてきた。
富山から上京して見舞いにきた叔母が、
「ほら、健ちゃん! ばあちゃんの手握ってあげて」
と言った。
祖母の手を握りながら感じていた気持ち。
9歳だったから、その感情がどういうものなのかはわからなかったが、今思うとそれは後ろめたさだったように思う。
死に瀕している祖母に、感情移入できない自分。
去来する思い出がない自分。
それなのに、深刻なフリをしなくてはならない自分。
その後祖母は奇跡的に持ち直し、1年以上生き延びた。
もし、発作を起こしたあの時に祖母が死んでいたら、自分はどう思っただろうか。
手を握ることに後ろめたさを感じたまま、死んでいく祖母を見たら、まるで自分がその死に荷担したみたいに思ったかもしれない。