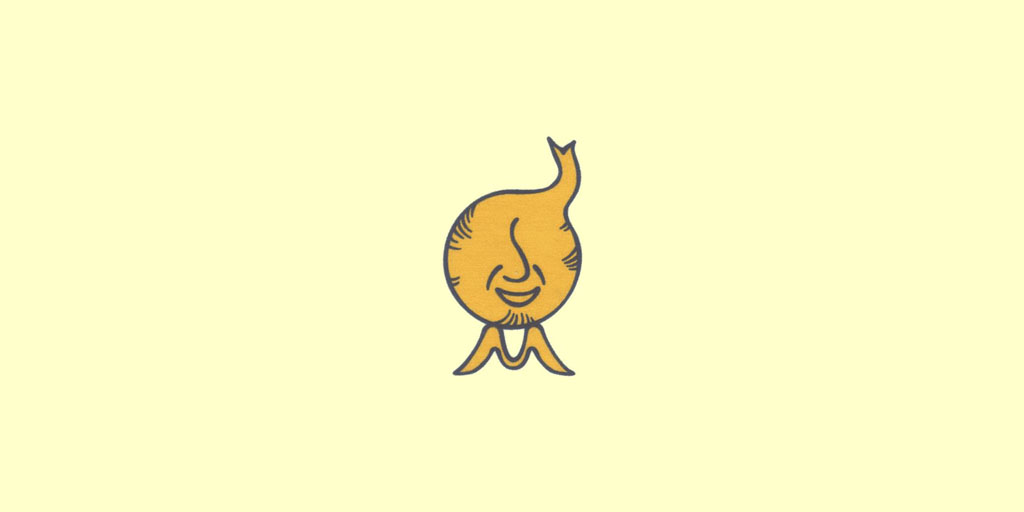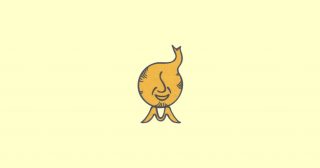何時なのかわからないが、外が暗い時間に目が覚めた。
昨夜は12時過ぎに寝たので、5時間眠ったとして5時だ。
休日のそんな時刻に起きてどうするんだと思いながら、もう一度眠気を待っていたが、20分ほどは寝台に横たわり、冴えた頭で色々なことを考えていた。
SMAP解散のこととか、美味しいカステラの作り方とか、スライムをラスボスにするゲームのシナリオとか。
再び眠り、今度は8時に起きた。8時なら不満はない。
ビデオ編集は終わったのだが、見直すと、いじりたい箇所が出てくる。
主に、アングル関係だ。
やり始めるときりがない。
11時、突然眠くなった。
催眠術にかけられたかのような眠気だった。
寝床で横になると、素直な眠気が、まるでファンクバンド「在日ファンク」のボーカルみたいな姿で玄関から入ってきた。
在日ファンクは、本当にカッコイイのに、バンド名で損をしていると思う。
2時に起きた。
腹が空いた。
バカの一つ覚えみたいに、「中華料理タカノ」へ。
お母さんから、
「(昼は)3時までです?」
と言われる。
オーケー。じゃあ、がっつり食ってやろうじゃないか。
「チャーハン大盛り」
レンジ前の息子さんがメニューを復唱する。
「ちゃああはん? 大盛っ?」
この復唱が、このお店の味だと思っている。
チャーハン大盛りは、かなりのボリュームだったが、3時丁度に完食した。
阿佐ヶ谷のミニストップへ行き、電気グルーヴのライブチケットを購入。
3月のだ。
3時半帰宅。
中島梓『小説道場』3巻読み進める。
単行本は全4巻なのだが、どういう形で終わったのか気になっている。
中島梓、つまり栗本薫の、90年代半ば以降の『グインサーガ』における変化は、リアルタイムで知っている。
なにが、どうなって、ああなったのか、そのへんの手がかりを、『小説道場』は示すのか示さないのか。
ただ、1巻と2巻と読み終えた今思うのは、90年代以降の「時代の空気」みたいなものは、中島梓にとっては決して心地よいものではなかったんじゃないかということだ。
理由はなくそう思う。
作者と読者の距離感が、テクノロジーの発達によって、どこか「容赦のない」ものになっていったこととか。
オレ自身かつて『グインサーガ』の熱心な読者であったがゆえに、強めの感情を抱きつつグインから決別した過去があったので、中島梓名義の作品を読むと、後ろめたさに似たような思いを抱いてしまう。
栗本薫の背後にいる、作家本人の自我に近い中島梓の存在感に、この人も人間なのだなと思わせるシンパシーを感じ、問答無用で切り捨ててしまったような後ろめたさ、だろうか?
小説に限らず、絵画彫刻音楽漫画映像舞踏演劇、表現をつきつめるとかならずおのれの中からこんな問いが返ってくる。
「なぜ、お前は、絵画(その他すべて)なのか?」
幻冬舎の見城徹さんは、小説を書くことについて、
「書かないと死んじゃうから書くんです」
と語っていたが、つまりそういうことだろう。
オレも死ぬんだ。いつか。
問題は、その瞬間にそれまでの自分を振り返る時、いつわりがあったかどうかだろう。
いつわりがあったまま死んだら、たぶんそれは、地獄行きみたいな気分じゃないだろうか?
でも、人間はずるいから、いつわりだらけで生きている人間は、その言葉を自分自身にかけることで、
(オレは、間違ってなかった)
っていうふうに、臨終を迎えるのだろう。
それを見ている周りのやつらが、
(いやいや、間違いだらけだったよ)
と、心の中で突っ込んでいるのも知らず。
夜、風呂に入り本を読み、天気予報を調べ家事をするうちに、12時になった。
明日は雪なのか?
地下鉄使えば余裕だぜ。
いっそ、メートル単位で積もってしまえ。
雪のたび毎回思う。