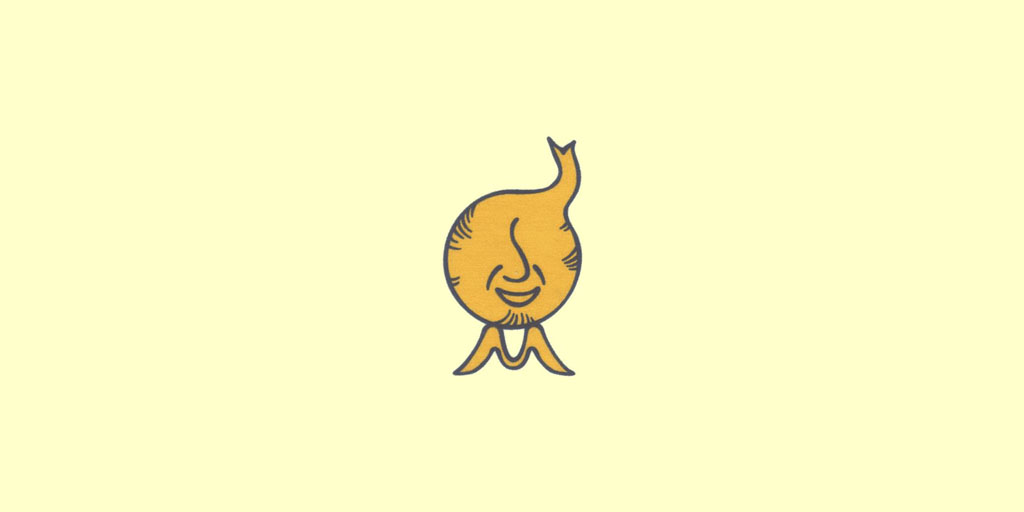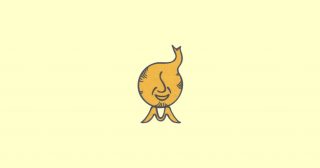朝、「いだてん」「たいむとんねる」の録画を見る。
実家に「今日帰る」とメールをすると、「今日は熱っぽいので日を改めよ」と返信。飯くらい自分で作れるが、それだと帰る意味はない。何々を食べたいと伝え、作ってもらうということが肝心なのだ。
「じゃあお前、お粥でも作ってやったらどうだい?」
十数年、週一で実家帰りをする身として言わせてもらうと、その孝行は違うのだ。それをやると、うちの親は早く死ぬ。
オレがお粥を食べたいと思って、作り、それを「食う?」と聞き、「食べたい」と言えば分ける。そういう形でないといけない。そういう形でないと、続かない。続かなくては意味がない。
昼、談志のムック本を読む。
中村勘三郎、三谷幸喜との対談がとてもいい。三谷幸喜には冒頭いきなり「新撰組!」はつまらないというようなことを言う家元だが、けなすのは本意ではなく、話が三谷さんに合わせるように映画の話になっていくところがいい。勘三郎とはひたすら芸談。こういう会話ができる年下の落語家が欲しかっただろうなと思わせる。
夕方、TSUKASAでサツマイモを買った。品種は紅あずま。昨日と同じだ。
昨日買ってきたものは170度のオーブンで3時間焼いたのだが甘くならなかった。今までうまく焼けなかった焼き芋はすべて紅あずまだ。
芋が原因なのか焼き方が原因なのか突き止めたいと思った。
140度のオーブンで90分焼いてみた。触ってみるとまだ固かったので、温度を変えずに60分追い熱をした。
結果は昨日と同じだった。ほくほくと言えなくもない加減だったが、甘みはなかった。
温度が高すぎるのだろうかと思い、次の芋を100度で150分焼いてみた。しかし、前の芋を焼くのに150分かかっている。次の芋が焼けるのは真夜中だ。焼き具合の検討は明日の朝することにした。
芋を焼いている間、腱トレ、スタディサプリ、Progateなどをした。あえて、興味があることを全部やってみた。そうすることで脳がどのくらい疲弊するのか確かめたかった。
最近、プログラミング言語の文帽を複数言語分いっぺんに調べている。制御構文を覚える時、各言語の記述法を横に並べると、相違点という差分が出来る。一つの言語だけを覚えようとするとそれがない。差分があった方が覚えやすい。
これって、外国語を習得する時も同じではないか? 英語と並行してフランス語を覚えた方が覚えやすいのなら、学習の初期段階でそうした方がいいのではないか?
覚えるといえば、先日、台詞覚えについて稽古場で話した。
自分の場合、家で台本を沢山読むより、稽古場で誰かにプロンプターをやってもらった方が覚えるのが早い。2011年7月に一人芝居をやって時など、台本を作った翌日、手伝いにきてくれた安見君にプロンプをしてもらって、三回繰り返すことでほぼ入った。
落語家は、師匠に目の前でやってもらうのを見て、新しい噺を覚えていく。つかこうへいは、口立てで役者に台詞を覚えさせた。口から耳というルートの方が台詞は覚えやすいのかもしれない。つかさんの場合、台詞の頻繁な変更を可能にする、理想的な方法論だったのだろう。
テキストをスタート地点にする芝居の作り方の方が歴史は浅いはずだ。つかさんの方法の方が芸能の始原に近いということだ。
テキストと舞台作品はレシピと料理の関係にある。目的は料理を完成させること。そのためにレシピは重要だ。しかし化学実験並みの精密さで大さじ小さじの分量を量ったりするからといって、料理が美味くなるとは限らない。
レシピと料理の間には、味見という人間的な作業がある。たとえレシピと少し違っても、人間的判断で味加減を調整することで、料理と人間の距離が縮まる。
演劇でも同じことで、台本に書いてあることはすべて正しいという考えを、よく考えずに実行しようとすると、その人は「困った人フォルダ」に入れられることになる。
かといって「だからおれは台本なんか信用しねえ」と言い放ち、目分量で芝居を作る人もまた同様のフォルダに入れられる。できた芝居はきっと、ジャイアンが作った料理みたいになるだろう。