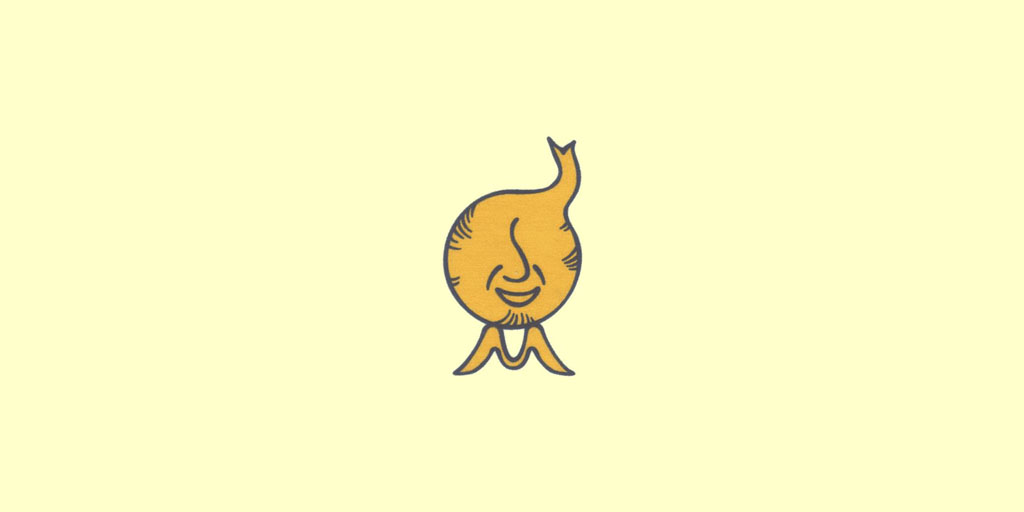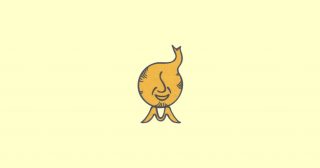暑さ継続。しかし太陽は五月の連休後より低くなってきた。
空気が熱いので真夏が続いているような気になるが、気圧相撲の結果次第ではあっという間に秋がやってくるだろう。丁度いい秋の期間が年々短くなっている。
昨日は走らず、今日も夕方走るチャンスを生かさなかった。急に面倒くさくなってしまった。
夜、『あしたのジョー』を全巻読み返した。
1巻をちょこっと眺めるつもりだったのだけど、面白くて一気に読んでしまった。自分が70年代好きであると自覚してから初めての読み返しだったため、面白いと感じるポイントが昔と違っていたからだろう。
9巻から12巻までのジョーは、力石を死なせた罪悪感から顔面へのパンチが打てなくなり、ボクサー廃業の危機に直面する。それでもジョーは、ドサ回りのボクサーに身を落としてまでボクシングにしがみつく。ここがジョーのどん底だろう。
しかし、ドサ回りのエピソードに、他のボクサー達と一緒の旅館に寝起きする描写があり、それが不思議と心落ち着くものだった。殺伐としていた少年院と似ているのに、ジョーは暴れず、ただ渇き、満たしてくれる何かを求めていた。
あと、リーダー格のボクサー・稲葉がとても良い味を出している。
8巻までのジョーは精神的にまだ子供だったが、このドサ回り編を経て、14巻でカーロス戦を終えたあたりから、自分にとってボクシングとは何かということについて思索を深めたように思える。
林屋の紀ちゃんとのプチデートで「真っ白な灰」の話をするシーンがとてもいい。のちに白木葉子から「すきなのよ矢吹くんあなたが!」という剛速球告白を受ける場面があるが、そっちより紀ちゃんとのシーンの方が恋愛物としてグッとくる。
でもカジ・センセ(©ブッチャー)的には、男のロマンがわからない平凡な女が去っていく場面の扱いなのかもしれない。ちばてつや先生が描いたから、染みる場面になったのだと思う。
そういえば白木葉子の告白って、次の連載作品『愛と誠』に似た何かを感じる。あれは、梶原一騎のテイストだと思う。
後楽園のゲームセンター、六本木のアマンド、首都高6号線らしき高架下と隅田川など、実際にある町を背景にした場面が増えていくのも、カーロス戦あたりからだ。これらが、1970年代の東京にタイムスリップした気分にさせてくれて、まことに楽しかった。後楽園ホールや武道館の場面など、みんな客席でタバコを吸っている。そういう時代だったのだなあ。
ちばてつや先生によれば、ジョーは死んだわけではないそうである。カジ・センセに示された原作は、葉子に見守られながらパンチドランカーの治療をするジョーが静かにたたずんでいるというようなエンディングだったらしい。まるで『Zガンダム』のカミーユみたいだ。
すべて読み返して気になったのは、太郎たちの見た目が1巻と19巻でほとんど変わらないということだった。
連載は5年続いた。現実の時間経過とぴったり一致しているわけではないが、それなりの年月が経過した描写もあるので、1巻から19巻まで5年以上はあると思う。ジョー、葉子、紀ちゃん、西は、それぞれ見た目も中身も成長したのに、太郎やサチはそのままだ。
サチなんか、本来なら19巻くらいで中学生になっていてもおかしくない。けっこう可愛い女の子になっているかもしれないのに。
そして子供たちは最終刊の20巻に登場してこない。ドヤ街の人々も。西も。紀ちゃんも。彼らは、ジョーの最後の試合を見ていない。
もしかして、子供たちやドヤ街の人々は、普通の人達には見えず、ジョーにだけ見える存在だったのではないか? 西は、紀ちゃんと結婚したために、そっちの世界の住人になってしまったのではないか?
そういえば1巻の最初で紹介されたその町は、架空の町みたいに演出されていた。
『子供たち実在しない説』は乱暴かもしれないが、連載の後半、本物の町が描かれるようになるにつれ、架空のドヤ街が存在感を失っていくのは、まことに興味深いことだと思った。
境目はやはり、9巻から14巻までのジョーの彷徨期にあるだろう。
そしてこの部分は、絶望しどん底に落ちた人間が苦しみ抜いて生きる道を見つける物語になっている。
『あしたのジョー』が、ボクシング漫画としてだけではなく、普遍的な人間ドラマの価値を持っているのは、9巻から14巻があるからだと、今日から言い切りたいと思う。力石が死んでから、カーロス戦が終わるまでを、自分のことだと思って、読むべし読むべし読むべし。