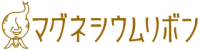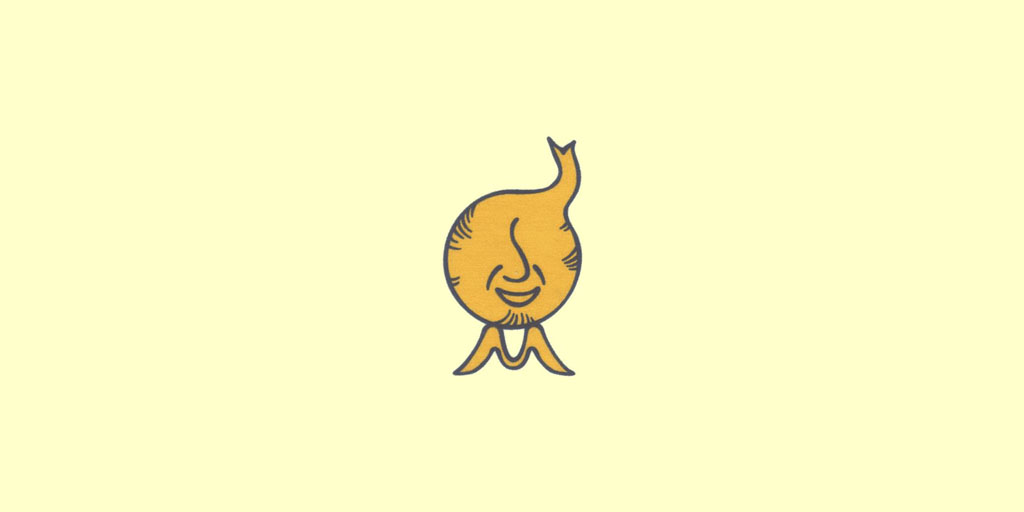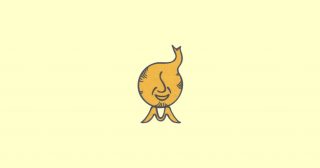黒澤明映画が急に見たくなったので、久しぶりに「椿三十郎」を見た。
1961年「用心棒」
1962年「椿三十郎」
1963年「天国と地獄」
1965年「赤ひげ」
この時期の黒澤明作品は、ただもうひたすらに面白い映画を作っていたように思える。
それはリアルタイムに同時代を生きていない者の感想かもしれないが、深く考えずに黒澤映画を堪能したいと思う時、この4作品のうちのどれかを選んでしまうのは、とっつきやすく面白いからだろう。
そういえばこの4作品は、種類も全然違う。
「用心棒」はダーティー・ヒーローが主人公の和製西部劇。
「椿三十郎」はコメディ要素の強いアクション活劇。
「天国と地獄」は誘拐事件を扱ったサスペンス。
「赤ひげ」はヒューマンドラマの集大成。
「用心棒」と「椿三十郎」は、主人公が同じなのに、その趣は違う。
「用心棒」が大ヒットしたので、東宝から続編をと言われて作ったのが「椿三十郎」だった。
そのためか、小品的味わいが強い。
ただ、この映画での黒澤明は、肩の力を抜いて持てる演出技術を伸び伸びとふるっている。
つまり、黒澤明のがもっとも純粋な形で現れているといえる。
キャスティングは適材適所。
小林桂樹の飄々としたキャラクター、仲代達也の眼光の鋭さ、加山雄三の育ちの良さ、伊藤雄之助の馬面、入江たか子の浮世離れした奥方ぶり、すべてニヤニヤ笑いしながら楽しめる。
「用心棒」から「赤ひげ」までの4作品があまりにも面白いために、その他の黒澤作品も同じ土俵で比較されがちだが、むしろこの4作品の方が特殊なのではないか。
この時期の黒澤監督は、黒澤プロという独立プロダクションを興し、作品を東宝に買い取ってもらうという形を取っていた。
つまり、この時期の黒澤明は、インディーズだったのである。
キネマ旬報のベスト10で、「ハウルの動く城」はベスト10に入っていなかった。
作品のでき云々ではなく、情報公開を規制したり、監督が公に出てこなかったりなど、そうした態度が嫌われたように思える。
作為的にランキングからはずしたみたいで、嫌な感じがする。
少し前、週刊文春が昨年のワースト映画を特集していた。
「デビルマン」や「キャシャーン」に加え、「ハウルの動く城」も入っていた。
しかし、いくらなんでもそれはないだろう。
「ハウル」をエンターテイメント作品に仕立て上げるのは、宮崎監督にとっては造作もないことだったに違いない。
前半でハウルが見せる格好良さは、明らかにエンターテイメント寄りの演出によるものだ。
なぜそれに徹しなかったのかを考えれば、ラストシーンなどはのように思えてくる。
今のところ宮崎監督は公の場で「ハウル」についてコメントしていない。
ほとぼりが冷めた頃に聞けるだろうか?
夜、スパゲティを茹で、水菜と納豆のサラダを食べる。
シナリオ年間選集を読む。
芝居の台本と違い、映画のシナリオは読んで映像が浮かぶようにできている。
だからむしろ芝居の台本より、読み物としては読みやすい。
そんなことを思った。