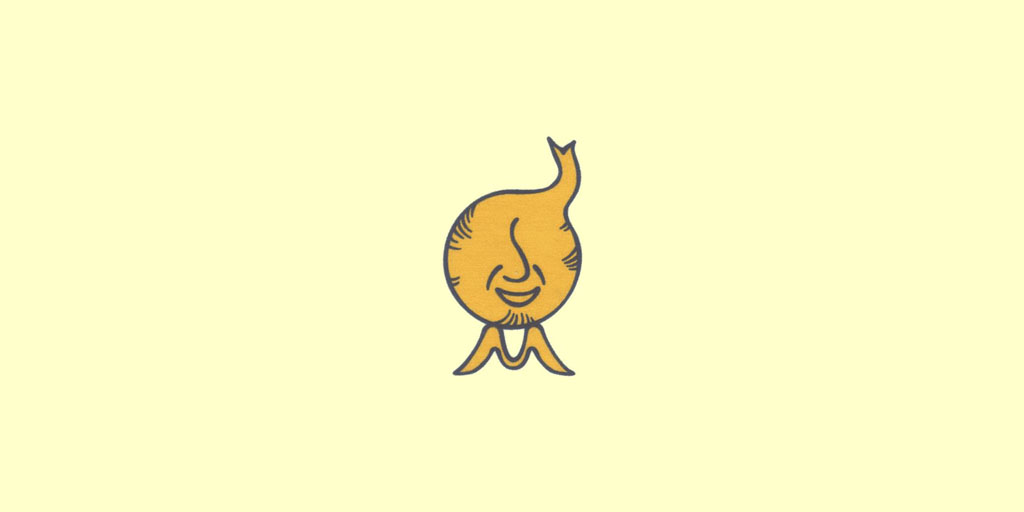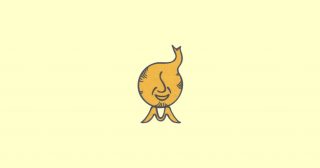朝、フルーツグラノーラとミルク。
昼は配達弁当を食べた。
色々なことがいちいち気に障り、気分は乱高下した。気にする対象はつまらないことばかりである。喋る時の抑揚だったり、そこからうかがえる感情だったり。
そんなものを気にするということは、オレの方が神経過敏になっているのだ。過去、何回そういう状態に陥ってきたことか。
イヤなもんはイヤだ。だから、イヤになるのは仕方ない。しかし、シーバス釣りにおいて、たとえば軽いルアーを投げる時、ルアーが左右どちらかにそれて飛んでいってしまうとする。その場合、投げながら指のリリースタイミングを調整して、まっすぐ飛ぶように工夫する。
イヤなもんはイヤだが、そう思う過程のどこかに、リリースタイミングに相当するポイントがあるのではないか。それを見つけるためだと考えれば、イヤだと思うことは、第一反応として正しい。「あちゃー、右に飛んでっちゃった」と同じことだからである。
夜、昨日と同じくホットドッグを食べた。
カート・ヴォネガット『ジェイルバード』読了。
主人公ウォルターは、大金持ちに雇われた運転手の息子だが、どういうわけかご主人に気に入られ、大学進学の金まで出してもらい、ハーバードを卒業する。
若い頃の彼は理想主義者で、共産主義にも染まったことがある。
戦争に行き、終戦後のドイツで、強制収容所から逃げ延びてきた娘ルースと会う。何ヶ国語も話せる彼女を通訳に雇い、やがて彼女と結婚する。
赤狩りの時代、友人がかつて共産主義者だったことを、そんなつもりじゃなかったのに結果的に告白し、友人は職を失う。
時が過ぎ、ニクソン政権時代、ウォルターは政権スタッフの一員になるが、ウォーターゲート事件後、収賄容疑で逮捕される。
妻に死なれ、息子には絶縁され、逮捕され、何年か経って出所するところからが、本編となる。
ウォルターには財産もない。迎えに来てくれる人もいない。刑務所時代、バーテンの資格を取ったので、どっかのバーで仕事ができないかと思っている。
そんな、徹底的に尾羽打ち枯らした老人が、かつて自分が告発した友人や刑務所で世話になった人、その他、親切にしてくれた人達ともども、おとぎ話みたいな展開の結果、大企業のボスになるという物語である。
この展開は、ヴォネガットが現実世界を徹底的にコケにしてやるために考えたのではないか。ざまあみろ現実、ってなもんである。
そう考えると実に面白い。70年代初頭、苦しみながら『チャンピオンたちの朝食』を書いたことを思えば、ずいぶん吹っ切れたものだ。
そして、この作品でヴォネガットは、自分の小説手法を完成させたのではないか。